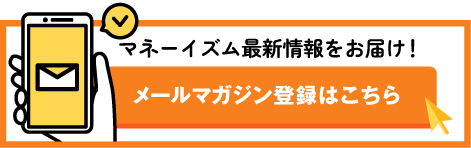従業員の毎日の通勤を企業が負担するために、多くの企業で通勤手当を導入していると思います。ここでは、この通勤費が厳密にはどのような扱いなのか今一度、詳しく解説していきます。
通勤費はどのような扱いなのか
そもそも従業員に給与を支払う際、企業はその支払う給与から所得税を差し引かなければなりません。これを源泉徴収と言います。ただし、企業が通勤費として従業員に支払う金額分に関しては、一定の限度額まで所得税が課されないという決まりになっています。
また、企業会計における勘定科目の分類では、通勤費はほかの手当や給与と同様に損金として算入することができるのです。
一方で、従業員の社会保険料や労働保険料に関しては、標準報酬月額や賃金総額と呼ばれている、企業が従業員に支払った給与等(定義はそれぞれ異なるため後述)に応じて支払額が決定します。当然この標準報酬月額や賃金総額には通勤費が含まれるため、通勤費が多いほど支払う社会保険料や労働保険料も多くなってしまうというデメリットもあります。
このように税金面においては一見お得そうな通勤費も、金額によっては総合的に得なのかをよく吟味する必要があります。
ここでは、通勤費がそれぞれの場合でどのような扱いになるのかについて詳しく解説し、企業にとっても従業員にとっても良い形になるような通勤費の申請の仕方について考えていきたいと思います。
所得税が課されない通勤費についてのルール
通勤費が源泉徴収を受けないためには、いくつかの条件があります。一般的に通勤手当は、公共交通機関の利用に対してしか支給されないものであると思われがちですが、自家用車や自転車通勤の場合でも源泉徴収されない手当として通勤費を支給することが可能です。通勤費が源泉徴収の対象外とするためには用いる通勤手段によって条件があります。
自家用車・自転車の場合の非課税限度額
自家用車あるいは自転車を利用して通勤する従業員の方に対して非課税で通勤費を支給できる限度額は、通勤に要する片道の距離によって決まります。それぞれの距離区分における非課税限度額は、以下の表のようになっています。
| 2キロメートル未満 | 全額課税 |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
| 55キロメートル以上 | 31,600円 |
もちろん、自家用車や自転車で通勤している従業員の方に、これを超えた額を通勤費として支払うことは可能ですが、それぞれの距離における非課税限度額を超過した分は通常の給与と同じと見なされ、所得税の課税対象となってしまうので、注意が必要です。
公共交通機関の場合の非課税限度額
公共交通機関を利用して通勤している従業員の方への通勤費の非課税限度額は、それぞれの従業員の方が会社に出勤するのに要する交通費あるいは通勤定期代です。この時とる交通経路は、距離・時間・運賃などを総合的に考えたうえで最も経済的かつ合理的なルートでなければなりません。新幹線を利用した場合でも、最も経済的かつ合理的であると判断された場合は通勤費として非課税下で支給することが可能です。ただし、グリーン車料金は非課税の通勤費に含めることはできません。また、とる交通経路が最も経済的で合理的であったとしても、1か月あたりの金額が15万円を超えてしまう場合、15万円を超えた分については給与の一部分として所得税がかかります。
その他の場合の非課税限度額
従業員の方の中には、公共交通機関と自家用車・自転車を併用しているという方もいるかもしれません。このような場合には先述の2つの規定を加算した形になります。自家用車あるいは自転車で通勤している区間の距離に応じた非課税限度額と、公共交通機関で通勤している区間の最も経済的かつ合理的なルートの非課税限度額を足し合わせた金額が、このような場合における通勤費の非課税限度額です。ただし、この合計が15万円を超過してしまった場合は、その超過分については給与の一部分とみなされ所得税がかかります。
社会保険料や労働保険料の計算における通勤費
通勤費は、所得税の源泉徴収の観点から見ると、非課税の手当として扱われていますが、諸々の社会保険料に関しては異なります。健康保険や介護保険、厚生年金など社会保険と呼ばれるものは、全て従業員の標準報酬月額に応じて決まります。標準報酬月額は、その月にその従業員が受け取ったすべての給与・賞与・手当等を含めるもので、通勤手当もこの報酬月額に含まれます。そのため、通勤費が多くなればなるほど社会保険料として支払わなければならない額は増えていってしまいます。
企業側の観点から言えば、従業員の社会保険料の金額が高くなろうと安くなろうとそこまで大きな関係はありませんが、従業員の立場から見れば通勤費によって支払わなければならない社会保険料が増えてしまうことは喜ばしくありません。
また、同様のことが労働保険料に関しても言えます。労働保険料は賃金総額と呼ばれる事業者が労働者に対して、賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対償として支払うすべてのものの総額をもとに計算されますので、当然通勤費が含まれています。
もちろん、会社の規定として通勤費は定額で何円しか支給しない、という形で定めることも可能なので、特に中小企業ならば従業員全体の傾向や状況を見つつ、それに応じて柔軟に通勤手当に関する規則を変えていくことも一つの選択肢ではないでしょうか。
会計科目において通勤費はどのように扱うのか
通勤手当を会社の会計科目で扱う場合、ほかの給与と同様に、損金として計上することができます。従業員に支払うものである以上、会社の経費とみなすことができるため、このような扱いになります。損金が増えるということは、その分だけ法人税の課税対象は減るため、通勤手当をうまく利用すれば法人税の節税につなげることも可能であるといえるでしょう。
例えば、法人税は現在、中小企業のうち年間所得が800万円以下の企業を対象とした軽減税率が導入されています(平成29年度の税制改正大綱にて平成31年事業度までの延長が発表されています)。一般企業あるいは年間所得が800万円より多い中小企業に対する法人税率が23.4%であるのに対し、軽減された税率は15.0%になります。そのため、通勤費の支払いによって年間所得を800円以上から800万円以下にすることができるのならば、通勤費は積極的に支払ったほうが良いでしょう。しかし、全従業員に全額支給するのは少々厳しいという場合もあるかと思います。そのような場合は、先述の通り通勤費は定額で何円しか支給しないという形で定めてしまうことで、支払う通勤費の総額をコントロールすることも可能です。
まとめ
通勤手当は従業員の働く環境をサポートするための大切な手当であり、源泉徴収の対象にはならずに会社の会計では損金として計上できるというメリットがある反面、社会保険料や労働保険料の計算の対象になる等のデメリットもあり、思っている以上に複雑です。どのような条件下で通勤費は非課税になるのか、そして会計上はどのような扱いになるのか、このようなことを管理するために多大なる労力を割くことが難しい事業者の方もいらっしゃるかと思います。そういった場合、税制のプロである税理士に気軽に相談することができる環境作りをお勧めします。